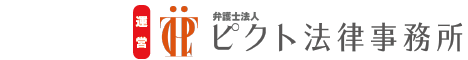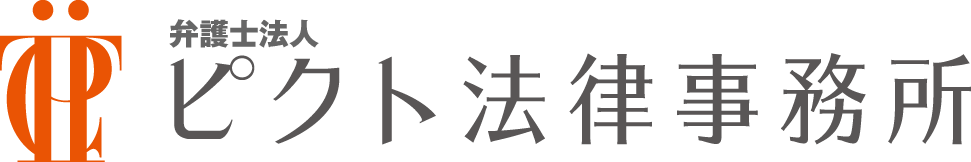業務委託契約でも雇用関係になる!?~注意すべきSEとの契約関係~
- 公開日:2019/2/7 最終更新日:2019/02/10
- 労務

IT系の会社では、その業務をシステムエンジニア(SE)の方に業務委託契約という形で、依頼されることが多いと思います。
業務委託契約というと、基本的には、請負や(準)委任契約であることを前提としているのではないでしょうか。
「請負」、「(準)委任契約」の内容については、契約の法的性質と作業内容の紛争~ソフトウェア開発紛争の解説③~において解説しています。
しかし、仮に名目上、業務委託契約としていても、実態は雇用であるとして、労働基準法その他の関係規定の適用を受けてしまうこともありうるのです。
雇用関係にあたるかどうかは、その業務実態などから判断されるため、契約書のタイトルを「業務委託契約」としているからといって安心なわけではありません。
今回は、雇用である場合に会社側に課される規制及びそれに反した場合の効果、雇用と判断されるポイントについて解説いたします。
[toc]
1 雇用となった場合の効果
雇用関係にあると判断される場合、法律上、以下のような労働法関係の各規制と、各種保険加入義務が生じます。
1-1 労働法関係規制の適用を受ける
まず、雇用関係においては、会社側から契約を打ち切ることについて厳しい規制がかかっています。
具体的には、雇用関係における契約の打ち切りは「解雇」にあたり、労働者側の帰責事由に基づく解雇等でない限り、即時解雇ができません(労働基準法20条1項)。
また、解雇理由も、客観的合理的な理由がなく、社会通念上相当でないと認められない場合には、解雇権行使が制限されることになります。
さらに、たとえ1年や3年といった期間を限定して契約していたとしても、その期間満了をもって、契約を打ち切ることについて、
- ・実質的には無期限の契約といえる場合
- ・労働者が雇用継続を期待することに合理性がある場合
には、期間満了による契約の打ち切りは、解雇と同様であるとして、前述の解雇権の制限と同じ規制がかかります。
これらのハードルは相当高いものです。
他にも、雇用関係と判断される場合には、最低賃金や割増賃金の支払い義務が課されることになります。(労働基準法28条、37条)
また、雇用関係であれば、労働時間の規制がかかります。
すると、所定労働時間を超えた労働に対しては、残業代を支払わなくてはなりませんし、休日に労働した場合も、割増賃金を支払うことになります。
そして、労働者に対しては、有給休暇を与えなければならないことにもなります(労働基準法39条)。
1-2 年金・保険関係への加入義務がある
雇用関係にある場合には、
- ・厚生年金保険
- ・健康保険
- ・労災保険
- ・雇用保険
など各種保険への加入が義務付けられます。
厚生年金保険及び健康保険については、その保険料を会社と従業員が半額ずつ負担することになります。(厚生年金保険法82条1項、健康保険法161条1項)
雇用保険についても、同様に会社と従業員の双方が負担します。
その負担割合は、労働者:使用者=1:2となっています(平成30年度の雇用保険料率)(労働保険の保険料の徴収等に関する法律31条1項1号)。
労災保険については、会社が全額負担しなければなりません。(労働保険の保険料の徴収等に関する法律31条1項1号、4項)
1-3 雇用関係と判断された場合に会社が負うことになる責任
雇用関係にあると判断された場合には、会社は以上のような各種規制及び保険加入義務を負うことになります。
したがって、雇用関係にはならない業務委託契約だと考えて、SEの方に仕事を依頼していたところ、事後的に雇用関係であると判断された場合、会社が負うおそれのある責任は以下のようなものがあります。
- ・解雇等無効による賃金支払い義務
- ・所定労働時間を基にした残業代や休日出勤の割増賃金の支払い義務
- ・労働基準監督署の指導や労働基準法違反による罰則の適用
- ・過去2年分の保険料支払い義務
事後的に解雇が認められない(無効)と判断された場合、解雇期間中は、会社の責任で従業員が働けなかったということで従業員は働いていなくてもその間の給料を受けとる権利があり、会社はこれを支払わなければならないことになる可能性があります。
また、所定労働時間を超過して働いていたことが立証された場合には、超過した分の残業代を過去2年間にさかのぼって請求されるおそれもあります。
業務委託は労働者ではないと考えて、長時間にわたる労働をしていた場合には、その額は莫大なものとなります。
また、このような従業員が1人ではなく、何人もいた場合には、その分積み上がってしまい、トータルの金額は計り知れません。
そして、以上の各請求については、支払いのなかった時から、年6%の割合の遅延損害金が請求されることになります。(商法514条)
また、悪質なケースでは、残業代の未払いについて、裁判所が付加金として未払い額と同額の支払いを別途認める可能性があります。その場合、単純に賠償額が2倍になるということです。(労働基準法114条)
さらに、【1-1の労働法関係規制の適用を受ける】で述べたような労働法の各種規制に違反していると疑われる場合。
労働基準監督署の調査・指導が入る可能性があるほか、違反が悪質と判断された場合には、会社代表者含め刑事罰に問われるおそれもあり得ます(労働基準法117条以下)。
保険料についても、雇用関係にあると判断されたときから保険料を負担すれば済むのではありません。
悪質と判断された場合や、行政の立ち入り検査を踏まえて加入させられる場合には、過去2年分の保険料をさかのぼって徴収されてしまうおそれがあります。(厚生年金保険法92条、雇用保険法74条等参照)
2 雇用関係にあると判断されてしまうポイント
雇用関係と判断されてしまうと、以上のような各種規制等を受けることになるほか、事後的に明らかになった場合には、さまざまな責任を負うことになってしまいます。
以下では、雇用関係にあると判断されてしまうポイントについて、見ていきたいと思います。
雇用関係にあると判断されるのは、その働いている人が「労働者」性を有している場合です。
労働基準法における労働者の定義は以下のとおりです。
第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
この労働者に当たるかの判断においては、以下のとおり、条文に規定のある二つの要素に加え、補助要素がいくつかあります。
- ①使用性
- ②賃金性
- ③事業性や専属性その他の補助要素
2-1 使用性~指揮命令関係~
使用性とは、簡単にいうと、使用者である会社の指揮命令を受けて働いていることです。
使用性の判断要素としては以下のものがあります。
- ・仕事依頼の諾否の自由の有無
- ・業務遂行上の指揮監督の有無
- ・勤務時間場所の拘束の有無
- ・代替性の有無
会社からの仕事の依頼に対して諾否の自由を有している(仕事の依頼を受けてもいいし、断ってもいい)ような場合、会社の指揮命令を受けていないものとして使用性は弱いと判断されます。これは重要な要素です。
これと関連して、業務を行う上で、業務の進め方などについて会社から具体的な指示を受けている場合には、使用性は高まってしまいます。
もっとも、通常の業務委託(請負や委任)でも、発注者が受注者に対して、発注内容についての指示を行うということはなされますので、指示をすることがまったく認められないわけではなく、「通常注文者が行う程度の指示」にとどまっているのか、「従業員に行うような詳細な業務指示」なのかがメルクマールとなります。
勤務時間や勤務場所が指定され、これに拘束される形態であれば、会社の指揮命令を受けているということにつながりやすく、使用性が高まります。
たとえば、他の従業員と同様に、定時に会社に出勤させて仕事をするように強制するような場合には、これにあたることになるでしょう。
代替性について、本人に代わって他の者が仕事をすること(再委託)や、補助者を使って仕事をすることが認められているなど、他人が代替できるような仕事をしている場合には、会社との指揮命令関係は薄いといえますが、代替性のない仕事をしている場合、会社からの指揮監督が働いているといえ、会社との指揮命令関係が強いといえます。
なお、これは、使用性の判断にあたっては、補助的な判断要素と位置づけられています。
2-2 賃金制~報酬と労務の対償性~
賃金性とは、労務と報酬とが対償関係にあることをいいます。
第11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
絶対的な基準ではないですが、報酬が時間単位で計算されるなど、労務提供の時間の長さに応じて報酬額が決まる場合には、労務対償性が強いということができます。
具体的には、一定時間の労働とそれに対する報酬額を決めており、働いた時間が足りない分を差し引いたり、逆に、超過した分を通常の報酬とは別の手当などで支給するという場合は、これにあたるかと思います。
他方で、時間ではなく仕事の成果に対して報酬が発生するようなら、労務対償性が薄く、請負や委任といった業務委託に近いものと判断されます。
報酬額は、依頼する仕事と紐づけられており、その仕事をするにあたりどの程度の時間がかかったかにより、報酬額が変動しないような場合です。
2-3 その他の補助要素
労働基準法9条のとおり、基本的に、労働者性は使用性及び賃金制を主に考慮して判断されるものです。
しかし、事案によっては、使用性や賃金制の要素がないとはいえないが強くないなど、この二つの要素だけでは判断が難しい場合もあります。
その場合には、以下のような補助要素をも考慮して労働者性を判断することがあります。
- ・事業者性の有無
- ・専属性の有無
- ・公租公課の負担
事業者性とは、機械・器具など業務に必要な道具を自己負担していたり、必要経費等を負担していたりする場合に、認められます。
指揮監督といった会社との関係ではなく、働く側が自らの計算と責任負担において事業を行う「事業者」としての属性に着目する要素です。
事業者性が強いと認められる場合には、労働者性が認められない消極的要素となります。
専属性とは、会社から他社の業務への従事が事実上制約されているかという要素です。
勤務時間場所の拘束がなくとも、契約などによって、他社の業務への従事が事実上制約されている場合、会社への専属性が強いとして、労働者性を認める方向の積極的要素となります。
公租公課の負担とは、源泉徴収の有無や社会保険料の控除がされているかなど、労働者性が認められた場合の効果に着目した判断要素です。
前述したとおり、労働者性が認められる=会社と雇用関係にある場合には、社会保険への加入義務があるので、これらを負担していることを前提とした行動を会社がとっている場合には、働く側の実態は請負等の業務委託ではないのではないかと推認しうるという意味で、労働者性を認める方向の要素となります。
まとめ
以上のように、契約の性質が、いわゆる業務委託契約(請負や委任)であるか、雇用契約であるかは、契約の名目ではなく、その実態を基準として判断しています。
近年、マスコミで過労死等の労働問題が大きく取り上げられることが多くなりました。
経費の削減が経営上重要なのは確かですが、それでも最低限守らなければならないルールがあります。
IT事業者の皆さまは、今一度、自社のSEを始めとする「業務委託契約」を結んでいる人たちとの契約関係が、実態としては雇用契約に当たってしまうのではないかということを確認してみてください。