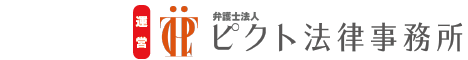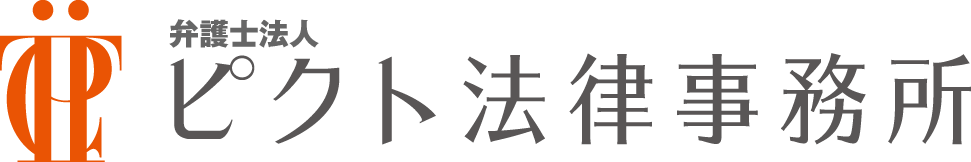IT事業におけるフレックスタイム制度~労働法改正の影響は?~
- 公開日:2019/4/25 最終更新日:2019/04/23
- 労務

平成31年4月1日、改正労働基準法が施行され、いわゆるフレックスタイム制も一部改正が入りました。
IT事業者の皆さんは、接客などの対人サービスが多くないため、フレックスタイム制を導入しているところもあるのではないでしょうか。
フレックスタイム制は、賛否両論あるシステムかとは思います。
しかし、会社の運用によっては、労働者にとっても魅力的な制度となるはずです。
今回は、そんなフレックスタイム制度について、改正のポイントも踏まえて解説します!
他の労働法改正についても別の記事で解説しています。
特に残業時間規制の記事は、今回の解説とも関わるので、ぜひ読んでください。
[toc]
1 フレックスタイム制の概要
「フレックスタイムって、名前は聞いたことあるけど、実際どういう仕組みなのかわからない。」
「うちの会社でも利用してるけど、実は細かいところはよくわかってない」
というIT事業者の方も、少なくないのかなぁと思います。
そこで、まずは、フレックスタイムの概要から説明したいと思います。
フレックスタイム制度とは、ざっくりと言ってしまえば、始業時刻と終業時刻を、労働者が決めて働くことができる制度です。
フレックスタイム制度の適用で変わるルールはこれだけです。
詳しく見ていきましょう。
1-1 労働時間
フレックスタイム制が適用された労働者は、始業時刻と終業時刻を自分で決めて働くことができるようになります。
この場合、勤務時間は1日8時間・週40時間以内という時間制限の原則は適用されなくなります(労働基準法32条の3第1項)。
どのような場合に時間外労働になるのかは、下記 で説明します。
この部分について詳しく知りたい方は、下記のリンクで詳細の解説へ飛びます。
【2 改正フレックスタイム制度のポイント】
・コアタイムとフレキシブルタイム
就業時間の決定について完全に自由にすることもできますが、多くの場合、コアタイム・フレキシブルタイムの設定をしていると思われます。
- コアタイム
- 労働者が1日のうちで必ず働かなければいけない時間帯
- フレキシブルタイム
- 労働者が自分で選んで、労働時間を決定できる時間帯
これらは、労使協定でかなり自由に定めることができ、曜日によって時間帯を変えたり、そもそも設定しなかったりすることもできます。
・深夜割増賃金
仮にコアタイムもフレキシブルタイムも定めず、労働者の選択に完全にゆだねた場合、労働者は深夜早朝に働くこともできるようになります。
この場合、会社側で気を付けなければいけないのは、 深夜の割増賃金は支払う必要があるということです。
フレックスタイム制は、あくまで、始業就業の時刻決定を労働者にゆだねているだけで、会社側の割増賃金の支払い義務を免除するものではありません。
したがって完全に決定を労働者にゆだね、超朝型の人・夜型の人が、深夜早朝に勤務した場合、割増賃金を支払わなければいけないのです。
労働基準法は、この点までケアしていないので、コアタイム・フレキシブルタイムを設定し、深夜早朝の時間帯は含まないようにした方がいいでしょう。
1-2 時間外労働と欠勤の扱い
フレックスタイム制のもとでは、時間外労働や欠勤の扱いが、通常の場合と違います。
一日ごと、一週間ごとではなく、清算期間として設定した期間を単位として判断されることになります。
・時間外労働
フレックスタイム制の場合、1日に8時間以上・週に40時間以上働いても、当然には時間外労働となりません。
清算期間を設定し、その期間の中で、法定労働時間超えて働いた部分が、時間外労働となります。
法定労働時間は、次の計算式で導かれます。
(清算期間の暦日数÷7)×40時間
40時間とは、通常の労働における1週間の上限時間ですね。
清算期間全体を通じて、1週間ごとの平均が、法律違反と同じ状態にならないことが求められているということです。
1か月単位であれば、法定労働時間は、概ね下のようになります。
| 28日 | 160時間 |
|---|---|
| 29日 | 165.7時間 |
| 30日 | 171.4時間 |
| 31日 | 177.1時間 |
清算期間中の総労働時間(通常の場合の所定労働時間に対応)は、この法定労働時間内で定める必要があります。
このあたりの仕組みは、通常の労働の場合に、1日の所定労働時間を8時間以内で定める必要があることと対応していますね。
フレックスタイム制においては、この清算期間全体の法定労働時間を超えて労働させる場合に、36協定が必要になってきます。
時間外労働規制との関係については、改正によって若干複雑になっていますので、下記で詳しくご説明します。
・欠勤
他方で、1日の労働時間がどれだけ短くても、欠勤とはなりません。
コアタイムを設定した場合でも、コアタイムに遅刻・早退したことが、当然には欠勤になりません。
清算期間の中で、総労働時間として定められた時間に達していない場合に初めて欠勤があったものと扱われます。
そのため、コアタイムの遅刻早退については、別途就業規則などで、人事査定などに響く旨を定めるなどして注意喚起したほうがよいでしょう。
1-3 休日と休憩
繰り返し強調しますが、フレックスタイム制では、始業・終業の時刻決定権が労働者にあるだけで、それ以外は変更されません。
休日・休憩についても同様です。
・休日
- ・休日を1週間に1日与える必要があること
- ・休日労働は、時間外労働規制において、単月100時間未満及び平均80時間以内の規制においてカウントされること
これらの規制は、通常の労働の場合と変わりありません。
労働者が自由に働けるからと言って、休日を与えなくていいわけではないのです。
・休憩
休憩は、労働時間に応じて、労働時間の途中に、労働者に一斉に与えられる必要があります(労基法34条)。
8時間を超える労働……60分
これはフレックスタイム制が適用される場合も同じです。
したがって、会社としては、「一斉に与える」という規制を守るためには、コアタイムを設定して、その中に休憩時間を設けることが考えられます。
また、労使協定によって、「一斉に休憩を与えない労働者の範囲」と「その労働者に対する休憩の与え方」について定めることも考えられます。
例外的な協定を結ぶ場合、会社側の管理がとても重要になります
フレックスタイム制のもと、労働者が変則的な休憩をとる場合、一斉にとるという動機付けがありません。
すると、労働者が休憩も取らずに6時間以上働く可能性もあります。
このとき、労働基準監督署に怒られるのは会社であって、労働者ではありません。
休憩については、会社は休憩を与える義務があり、労働者に休憩を取る義務はないのです。
1-4 有給休暇
フレックスタイム制のもとでも、有給休暇を取得させる必要があります。
しかし、フレックスタイム制のもとでは、1日の労働時間がまちまちになることが予想されますね。
そこで、フレックスタイム制を採用する場合には、1日の標準労働時間を定めることになります。
標準労働時間は、清算期間の総労働時間を、期間中の所定労働日数で割った時間を基準とします。
有給休暇を取った場合には、この標準労働時間だけ働いたものと考えて、賃金を与えることになります。
2 改正フレックスタイム制度のポイント
今回の改正では、先ほど説明しました清算期間を最大3か月にすることができるようになりました(労基法32条の3第1項2号)。
改正したフレックス制度は、同じく改正された残業時間規制との関係で、少し複雑になっています。
時間外労働規制の解説はこちらです。
2-1 清算期間が1か月の場合
フレックスタイムにおける法定労働時間を超える場合には、36協定の締結が必要になります。
1か月単位の法定労働時間は下のようになります。(再掲)
| 28日 | 160時間 |
|---|---|
| 29日 | 165.7時間 |
| 30日 | 171.4時間 |
| 31日 | 177.1時間 |
清算期間が1か月であれば、これを超えた分が時間外労働となり、原則として45時間を超えることができません(労働基準法36条3項・4項)。
また臨時的な特別の事情がある場合についての規制も同様です。
清算期間が1か月の場合、法定労働時間や時間外労働の把握の仕方が異なるだけで、それ以外の特別な規制はありません。
後ろで述べています労働者の労働時間の管理に気を付けてください。
2-2 清算期間が1か月を超える場合
清算期間が1か月を超える場合には、少し規制の内容が変わります。(労基法32条の3第2項)
・労働時間の上限
- ①1か月ごとの労働時間が、週平均50時間以内
- ②清算期間全体の労働時間が、週平均40時間以内
1か月ごとに把握される時間外労働(①)と、清算期間全体で把握される時間外労働(②)とがあるということです。
清算期間が1か月以上であっても、1か月ごとの時間外労働に制限がかかります(①)。
それが週平均50時間制限です。
清算期間が1か月であれば、週平均40時間であったところが、週平均50時間が限度となっています。
週平均50時間の月間労働時間は次の通りです。
| 31日 | 221.4時間 |
|---|---|
| 30日 | 214.2時間 |
| 29日 | 207.1時間 |
| 28日 | 200時間 |
加えて、清算期間全体について週平均40時間以内である必要があります。
【2か月の場合】
| 62日 | 354.2時間 |
|---|---|
| 61日 | 348.5時間 |
| 60日 | 347.8時間 |
| 59日 | 337.1時間 |
【3か月の場合】
| 92日 | 525.7時間 |
|---|---|
| 91日 | 520時間 |
| 90日 | 514.2時間 |
| 89日 | 508.5時間 |
これら①もしくは②の規制を超えて、時間外労働をさせる場合に、36協定が必要となり、その合計時間に規制がかかってきます
・時間外労働の上限
時間外労働の上限は、通常の場合と同じです。
つまり、清算期間にかかわらず、下記の規制がかかります(労基法36条4項、5項、6項)
①1か月あたり45時間以内
②1年当たり360時間以内
③時間外労働と休日労働を合わせて、1か月あたり100時間未満
④時間外労働と休日労働を合わせた時間について、直近の過去2ヵ月の平均、3か月の平均、4か月の平均、5か月の平均、6か月の平均が、すべて80時間以内
臨時的な特別の事情がある場合には、
⑤1か月あたり45時間までという原則的制限を超えて時間外労働ができるのは、1年あたり6か月まで
⑥時間外労働(休日労働を含まない)が、1年720時間以内
・時間外労働の把握
時間外労働については、各月で把握するものと清算期間の最終月でのみ把握されるものがあります。
週平均50時間を超える部分
・最終月で把握されるべき時間外労働
清算期間を通じた実労働時間から各月ごとに把握した時間外労働時間を除いた時間が、清算期間における法定労働時間を超えている部分
つまり最終月において、清算期間全体を通じた時間外労働が、文字通り清算されることになります。
最終月においては、週平均50時間を超えていない場合でも、清算期間を通じた時間外労働があれば最終月における時間外労働と扱われることに注意してください。
週平均50時間ばかり考えていて、
最終月に、時間外労働と休日労働の合計が100時間を超えてしまったり、
45時間超の時間外労働が、1年で7回以上行われてしまったり、
過去6か月の平均が最終月の時間外労働時間のせいで平均80時間を超えてしまったり、
様々な可能性が考えられます。
2-3 会社側の管理体制
以上説明してきたことからわかりますように、フレックスタイム制の場合、日々の労働時間をしっかりと管理しなければなりません。
労働者が決定する勤務時間を会社側が把握できる仕組みを作っておかないと、清算して初めて、法定労働時間を45時間超えて働いていたことが分かったなどという事態がありえます。
そのため、会社側としても、できる限り毎日、労働者の勤務時間を把握し、実労働時間が時間外労働規制にかからないかを管理する体制が必要です。
このような仕組みをとっていれば、実労働時間が所定労働時間に不足している労働者も同時に管理できます。
この点は、労働者の協力なくして実現できることではありません。
フレックスタイム制においても、会社側の主導で、日々の労働時間の報告を周知徹底したほうがいいでしょう。
3 フレックスタイム制度の活用
フレックスタイムはその活用法いかんによって、その評価が180度変わってくるといっても過言ではありません。
まずはフレックスタイムを利用するための手続きを見てから、活用法についてご案内します。
3―1 労使協定の届け出
フレックスタイムを利用するには、以下の事項について定めた労使協定を結ぶ必要があります。
また清算期間が1か月を超える場合には、労働基準監督署への届出も必要です。
- ・対象となる労働者の範囲
- ・清算期間
- ・清算期間における総労働時間
- ・標準労働時間
- ・コアタイム(任意)
- ・フレキシブルタイム(任意)
そのほかに総労働時間外労働(法定労働時間内)に対する割増賃金の支払いや、不足時間について繰り越しや欠勤と扱うことについての定めを置くことが考えられるでしょう
1か月を超える場合の届け出は必須であり、罰則もあるので注意してください(労基法120条)。
時間外労働をさせる場合は、別途36協定に関する届け出も必要です。
詳しくはこちらを参照してください。
3―2 フレックスタイムの利用
フレックスタイムが適用されるべきでない職種で、フレックスタイムを利用しても、結局時間拘束されて、いつもと変わらないということもあります。
例えば接客業を始めとした、お客様相手の事業で、フレックスタイムを利用しても、お客様対応のために出勤時間が変わらないこともありえます。
これは、フレックスタイム制度が悪いのではなく、会社のフレックスタイム制度の使い方が悪いのです。
正論も使い方を誤ればただの暴論でしかないのと同じです。
使い方を考えて使わなければ、簡単に批判されてしまいます。
もちろん労働者側が自己の都合で他の労働者を振り回すような使い方をする事例もあるでしょう。
しかし、その場合にも会社側が、お願いする限度では、不適切な活用を指導することができるはずです。
自社での活用を検討している、または既に自社で活用しているIT事業者の皆様。
先ほど述べたように、フレックスタイムの中身は適用範囲を含め、かなり自由に設計できます。
だからこそ自社でフレックスタイムを活用できるのはどの範囲か、どのように活用するかをよくよく検討してみてください。
まとめ
フレックスタイムもただ取り入れればいいという問題ではありません。
また導入にあたっては、労働者に対して、労働時間管理を徹底するよう周知するとともに、会社側がそれを把握できる仕組みは必須です。
これは、フレックスタイム制度の導入した場合に限った話ではありません。
法律の規制を受けているのは、労働者ではなく、会社です。
労働者に自由を与えることは、会社側が責任を負わないことと同義ではありません。
しかし、活用さえうまくいけば、労働者お満足度も上がり、会社の生産性を上げることもできる制度のはずです。
自社の中で活用することはできるのか、活用する範囲は絞ったほうが良いのか。
事業内容や部門ごとの仕事内容を考えて、適用範囲を検討してみてください。