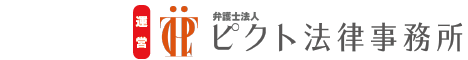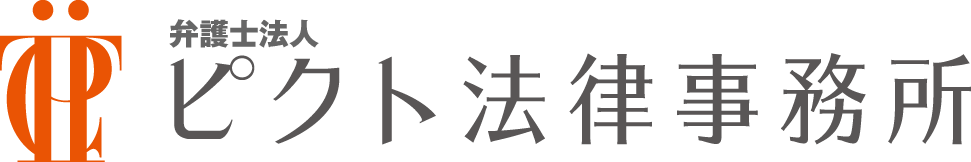従業員等が作成した著作物について、著作権法上の要件を満たした場合には、その著作者は従業員ではなく会社になります。これを「職務著作」といいます(「法人著作」ともいいます)。
職務著作は会社にとって便利な制度ですので、有効に活用するべきです。そのため、今回は、職務著作の要件と、実務上注意するべき点について解説します。
1 職務著作とは
著作権法15条1項は、次のとおり、従業員の作成した著作物は一定の場合に会社が著作者になるとしています。
(職務上作成する著作物の著作者)
第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
2 (以下略)
以下で、職務著作の要件について簡単に解説します。
1-1 法人等の発意とは
「発意」とは、一般に、著作物作成の意思が直接または間接に使用者の判断にかかっていることを意味すると言われています。これは、上司が部下に作成を指示した場合のみならず、部下がアイディアを出し、上司の了承を経てから部下が作成した場合も含みます。
1-2 業務に従事する者とは
会社と雇用契約を結んで働いている従業員のほか、会社の役員も「業務に従事する者」に含まれます。職務著作制度の目的が会社による円滑な著作物の促進にあるので、会社と密接な関係にある者の創作活動は会社によるものと同視すべきだからです。
よく問題になるのが、デザイナーやプログラマーとの間で業務委託契約を締結している場合です。これらの者と会社との間に雇用契約関係があるかどうかはよく争われますが、その場合でも、使用者(会社や上司)との間で著作物の作成についての指揮監督関係にあって、労務提供の対価が支払われていると評価できるのであれば、職務著作が成立するとするのが最高裁です(アニメのイラストレーターとの紛争について、最高裁平成15年4月11日判決があります)。
なお、この最高裁判決は、あくまで「雇用契約関係にあるかどうか」についての判断しかしておらず、雇用契約とは別の委任契約などの場合にも同様の解決基準で判断するとはしていません。ですが、その後の地方裁判所などでの裁判例では、業務委託の場合にも最高裁とほぼ同様の判断基準で処理するものが多くなっています。そのため、実務的には、業務委託契約の場合でも最高裁の基準が大いに参考になります。
1-3 職務上作成とは
著作物の作成がその従業員等の職務に関して行われたことが必要です(「職務上作成」)。この関連性が認められる限り、仕事を自宅に持ち帰って作成した資料などについても職務著作が成立する可能性があります。
1-4 公表名義とは
従業員等が作成した著作物を会社の名義で公表する場合に、職務著作が成立します(「公表名義」)。具体例としては、会社の紹介パンフレットや、会社から販売する商品のデザインは、会社名義で公表されています。
ただし、外部に公表しないからといって、職務著作の成立が論理必然的に否定されることにはなりません。例えば、商品の設計書や仕様書は、確かにそのままでは会社外部には公表されません。ですが、「公表名義」の要件は、公表は予定されていないが、仮に公表されるとすれば法人等の名義で公表されるものも含まれます。そのため、会社内部でしか使わない設計書等にも、職務著作が成立する可能性があります。
なお、プログラムが著作物である場合には、この「公表名義」の要件は不要です(著作権法15条2項)。そもそもプログラムは公表されないことも多いですし、公表されたとしても会社の名称などは普通表示されないからです。
1-5 別段の定めとは
著作権法15条1項は、最後の要件として、「その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない」ことを求めています。
これは、労働契約や就業規則の中に「別段の定め」、つまり「従業員が著作者となること」が記載されているとそっちが優先されますよ、ということです。
あまり労働契約書や就業規則の中にこのような別段の定めがあるケースは多くありませんが、たまに入っていることもありますので、ネットから拾ってきた就業規則をそのまま使っている方がいたら要注意です。
2 職務著作が成立すると・・・
職務著作が成立すると、著作物の作成者(=著作者)が会社等になります。つまり、その著作物の権利はすべて会社等が取得することになります。
そのため、会社がその著作物を販売したり公表したりするときに従業員の許諾は不要です。また、第三者がその著作物の利用許諾をもらうときには、従業員個人ではなく会社からもらうことになります。
このように、職務著作は会社にとって非常に有益な制度なのです。
3 実務上の注意点
職務著作が成立する範囲は広いですが、前述の要件の箇所で個別に説明したとおり、いくつも注意点があります。
特に注意するべきなのが、「業務に従事する者」という要件です。
前述のとおり、業務委託の人も職務著作が成立する可能性はあります。ですが、著作物の作成に指揮監督関係が必要で(仕事の指示に基づいて作成しないとダメ)、労務提供の対価がきちんと支払われていること(安すぎる報酬は職務著作を否定する方向の事情になる)に注意してください。これらの条件をクリアしないと、会社ではなく従業員等の個人が著作者になります。
また、業務委託を受けた従業員等の側から、後になって「あの作品の著作者は自分だ」と主張されるリスクもあります。このリスクに備えるため、「業務に従事する者」であることについて、次のような証拠を残しておくことが重要です。
-
残しておくべき証拠
- ・会社からの発注があったことを示す資料
- 例:発注書、仕様書、契約書等
- ・業務委託内容を会社側から提案していることがわかる資料
- 例:発注書等、打合せの議事録、創作の方向性についてのメールのやりとり等
- ・労務提供の対価が支払われていることがわかる資料
- 例:報酬基準や報酬明細書等
4 まとめ
今回は、会社にとって非常に便利な職務著作について解説しました。
今まで「なんとなく会社が著作権を持っているだろう」と考えていた事業者の方は、本当に職務著作が成立しているか、確認されることをオススメします。