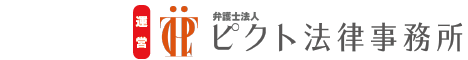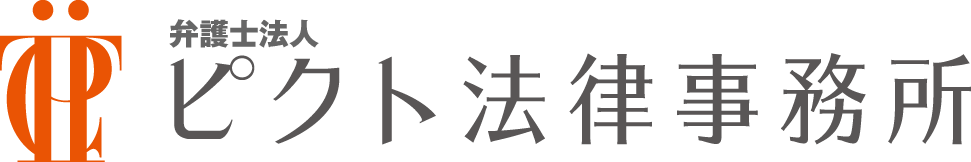IT・EC事業者の方は、会社の紹介や商品の通販のためにウェブサイトを作成することが多いです。そして、そのウェブサイトの作成のために、専門の外部のベンダーに発注したり、自社のスタッフにウェブサイト作成の指示をしたりするなど、多額の費用やコストをかけることも多いです。
しかし、ウェブサイトで使用されているプログラムを同業他社に模倣され、顧客を奪われるなという問題が生じる可能性があります。このとき、模倣された事業者は、そのウェブサイトで使用されているプログラムが著作物であるとして、著作権侵害に基づく差止請求を行うことはできるのでしょうか。
今回は、ウェブサイトで使用されるプログラムが著作権侵害だとして争われた裁判例のうち、HTMLの著作物性が問題となった事例を解説していきます。
1 事案の概要
ベンダーである原告(控訴人)が、ウェブサイトで使用する通販管理システムを機能させるためのプログラム(本件プログラム)を作成し、これをユーザーである被告(被控訴人)に納品して、契約期間内にのみ使用を許諾していました。しかし、被告が、契約で定めた期間を経過しても本件プログラムを使用し続けたため、原告が、著作権(複製権)侵害を理由に損害賠償請求訴訟を提起しました。
原告は、本件プログラムのうちのHTMLの部分は、原告が独自に作成した著作物であるから、被告が使用している本件プログラムは著作物だと主張しました。
これに対して被告は、HTML部分はありきたりな表現方法で作成されているので、プログラム全体が著作物には当たらないと反論しました。
2 プログラムの著作物?
プログラムも、一定の場合には著作物に該当します。
前回の記事(退職者が会社のプログラムを無断で持ち出した場合に起きるトラブルとは)で詳細に解説しておりますが、「プログラムに著作物性があるというためには、指令の表現自体、その指令の表現の組合せ、その表現順序からなるプログラム全体に選択の幅があり、かつ、それがありふれた表現ではなく、作成者の個性が表れたものである必要がある」と定義されています。
3 裁判所の判断はどうなったか
上記の事案で、裁判所は一審も二審も、本件プログラムのうちのHTMLの部分は原告の独自性が発揮されていないから著作物ではなく、したがって本件プログラムも著作物ではないとして、損害賠償請求を棄却しました。特に、二審の知財高裁が、HTMLを詳細に分析して著作物性を判断しているので、以下では、知財高裁の判決を紹介します(知財高裁平成29年3月14日判決)。
3-1 知財高裁の判断手法
知財高裁は、本件プログラムが通販管理システムの中で使用されるものであること、デザインや表示文言などがユーザーが決定して発注していることを念頭に置いています。そして、HTMLの各テキストがそれぞれ特定の指令を出す役割をしていることから、HTMLの各テキストを別個に抜き出し、そのそれぞれの著作物性を判断しています。
3-2 判断のための重要な証拠
知財高裁は、知的財産権の裁判を専門に扱う部署ですので、知的財産権に関する法律(特許法、著作権法、商標法、意匠法、不正競争防止法など)に非常に詳しい裁判官がおります。ですが、知財高裁の裁判官といっても、物理や化学、あるいはプログラミングなどの技術的な面に非常に詳しいとは限りません。
そこで、自らの作成した商品や発明に独自性があることを裁判官に理解してもらうため、辞典や教本などが有効な場面があります。特許権に関する裁判では、広辞苑がよく証拠として提出されます。
本件でも、裁判官が各テキストの著作物性を判断する際に参考にしたのは、HTMLに関する辞典や教本でした。
3-3 著作物性の結論
裁判官は、HTMLについての辞典や教本を参考にしつつ、原告が作成した各HTMLに原告の独自性が発揮されているか、ありふれた表現になっていないかを判断していきました。その結果、すべてのテキストについて、「HTMLに関する教本及び辞典に記載された記述のルールに従った、作成者の個性の表れる余地があるとは考え難いものや、語義からその内容が明らかなありふれたものから成り、したがって、作成者の個性が表れているということはできない。」と判断しました。
4 ベンダーはどのように対処すれば良いのか?
上記のようにHTMLの著作物性が否定されることは非常に多いと思われます。もちろん、事案によってはHTMLが著作物であると認められる可能性もありますが、著作物性が認められるのはなかなか難しいと考えられます。そして、上記の事案のように、プログラムの著作物性がもっぱらHTMLの創作性に依存しているような場合には、プログラム全体についても著作物性が否定されるおそれがあります。そうすると、もはや著作権法による救済を受けることはできません。
そこで、ベンダーは、ユーザーとの間の契約において、プログラムの扱いについて明確に合意しておくことが必要です。
契約書で決めておくべき事項としては、ユーザーが納品されたプログラムを使用できる期間、その期間を過ぎたらベンダーはユーザーに対しプログラムの使用の差止めを求めることができること、ユーザーが差止請求を無視した場合のペナルティ(違約金など)が考えられます。
このように契約書で定めておけば、プログラムに著作権が認められなくとも、裁判所では「契約に基づく権利」を主張することで救済を受けることができる可能性が高まります。
5 まとめ
上記の判決から、ウェブサイトの模倣の際に、そのウェブサイトを表示しているHTMLの著作権を主張するのは、難しいところがあります。HTMLは、一定の言語であって、そもそも独自性を発揮できる部分が少ないものであり、また、むしろHTMLに著作権を認めてしまうと権利を主張できる範囲が不当に広範囲になってしまうという懸念もあります。
もし自社のウェブサイトが模倣されたら、多くの場合、HTMLの著作権ではなく、画像などの著作権に基づいて損害賠償請求をしていくことになるでしょう。また、ユーザーとベンダーの間のトラブルであれば、まず事前に契約書でプログラムの扱いを決めておくことが重要です。